立春、雪下ろし
2月4日(水)、多聞館では雪下ろしを行いました。
近年は降雪量が少なかったので、4年ぶりの雪下ろしです。
月山佛生池小屋主人の工藤さんを中心に、これまでにも何度か来ていただいている方たち4人で作業を行っていただきました。
この冬は厳しい冷え込みがなかったので、氷のような固い層はなかったようですが、雨が入ったりしたので、下のほうには重い層が厚くあったようでした。また、ここ3日ほどに振った新雪もかなりのボリュームがありました。下ろし終わってみれば相当な積雪量だったことに改めて驚きました。
工藤さんたちとの話では、ここにきて急に雪下ろしの依頼の連絡が立て込んできたため、なかなか回り切れない状況だそうです。この地域で雪下ろし作業に当たれる人が減ってきていることも拍車をかけているようです。そういえば今時点で雪下ろしを終えた家はそれほど多くないように感じます

この日はちょうど立春。母は、「立春に猫の足がくぐるほど雪が降ると大雪になる」ということをよく言いますが、そろそろ春の兆しが見えてきてほしいものです。
雪下ろしに当たってくださった皆様、ご苦労様でした。


































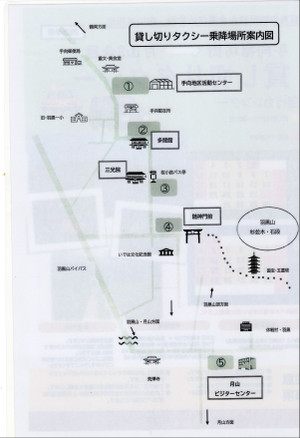


最近のコメント