
図司呂丸(ずしろがん=俳号)は本名を近藤佐吉といい、現在の鶴岡市鳥居町の藩士の出であったといいます。
後に羽黒町手向の現在の羽黒第一小学校の傍に居宅を構え、山伏装束の染物を生業としつつ、妻と共に俳諧に親しんでいた人物と伝えられています。
奥の細道紀行で羽黒山を訪れた松尾芭蕉一行は、最初に呂丸の元を訪ねました。
そして呂丸の取り計らいにより、羽黒山の別当代であった会覚阿闍梨との面会を果たし、その後7日間にわたり当地に滞在し、出羽三山参拝をも果たしています。

芭蕉は本坊宝前院若王寺で催された句会において
《有難や雪をかほらす南谷》
の句を残しました。
(←本坊跡)
羽黒の地でと呂丸と過ごした時間について芭蕉は後に呂丸に寄せた書簡の中で、
《誠不思義清談夢之心地仕候》(=今になってみると不思議なことですが、あなたとお会いしてお話した時間は夢の中の出来事だったように感じます)といい、
《命候内には今一度と願申候》(=私の命のあるうちに今一度お会いしたくお願い申し上げます)
とまでしたためています。
呂丸と芭蕉との心の交流がうかがえます。

(←南谷)
芭蕉の招きに応じて江戸を目指した呂丸は、芭蕉との三年ぶりの再会を果たし、旧交を温めます。
まだ発表前だった「三日月日記」の稿本を貰い受けたりもしています。
その後、呂丸は西方への旅を続けましたが、京都において病に倒れ亡くなりました。
 辞世句 《消安し都の雪ぞ春の雪》
辞世句 《消安し都の雪ぞ春の雪》
その知らせを聞いた芭蕉は
《当帰より哀れは塚のすみれ草》
の追悼句を送っています。
上の写真は多聞館近くの『烏崎稲荷神社』境内に祀られている図司呂丸追悼句碑です。
野に埋もれていたものを多聞館の先々代(土岐多聞)をはじめとする地元有志があらためて祀ったものです。
先日紹介した『図司呂丸顕彰俳句大会』のルーツがここにあります。
ちなみに、上の由縁書は先々代の筆によるものです。
 近年は、「奥の細道」を訪ねて当地を訪れるお客様も多くいらっしゃいます。
近年は、「奥の細道」を訪ねて当地を訪れるお客様も多くいらっしゃいます。
その折には、羽黒の地で芭蕉を迎え、心の交流を深めた図司呂丸という人物がいたことにも思いを馳せていただければ、と思います。
 ←〈ポチッ〉とクリックのご協力をお願いします。
←〈ポチッ〉とクリックのご協力をお願いします。
多聞館ホームページ トップへ























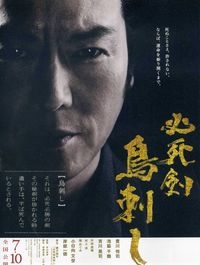




























最近のコメント